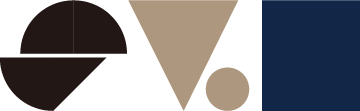今回のブログは前回に続き、有田焼のヒストリーをお伝えします。
1829年、佐賀藩の10代藩主であった鍋島直正は、文政の大火という当時起きた大火災により大きな被害を受け、経済的窮地に陥った藩の財政を立て直すことに奮闘していました。火災が起きるまで、佐賀城下に蔓延していた奢侈贅沢の風潮を戒め、質素倹約に努めるように「倹約令」を発し、人民に対しては朝は味噌汁と漬物だけ、昼と夜は干し魚か魚の煮焼きの物程度の粗食を常とし、衣服は木綿のみと厳しい決まりで統治していました。直正自らも朝食は一汁一菜とし、洗いざらしの木綿の着物を着て範を示していたそうで、こうした背景からも当時の切迫した状況が伺えます。
倹約令は有田皿山の窯元と伊万里の商人らにも及んだそうで、好況の時は競うように贅沢のかぎりを尽くし、幕府からも優遇されていた窯焼と職人たちも、不況になると窮乏を極めるという状態を繰り返すようになりました。儲かるときにはとことん儲かる窯元の職人たちの間では、貯金という概念は蔑視されており、数十年先の暮らしを安定させるための蓄えを持つ、という考え方は一般的ではなく、皆が贅の限りを尽くしていました。

しかし、藩の経済状況が悪化すると、職人の流出や粗悪品の流通を招き、有田のブランドに傷がつく可能性があったため、藩の重要な産業を守っていくためにも、窯業関係者らも質素倹約・貯蓄・勤勉に努める必要があったと言われています。
同時に、有田皿山の窯業経営の健全化は、佐賀藩の経済成長に置いて欠かすことのできない要素であり、その資金調達を叶えるべく当時の日本ではオランダ貿易にも積極的に取り組んでいました。
この頃日本はまだ公式には鎖国しており、オランダ貿易は藩命を受けた久富与次兵衛と田代紋左衛門に限って行われていました。厳しい状況下で行われた輸出政策でしたが、この時期の輸出産業は優先課題であった経済成長・近代化をしていくための資金繰りにも大きく貢献したほか、藩財政に大いに貢献しました。また、この頃の貿易経験を通じて、ヨーロッパ人の好みを把握していたことは1867年のパリ万博以降の商機につながりました。

直正が財政再建と近代化に全力を注いでいる頃、江戸幕府はペリー来航(1852年)を経て1854年にアメリカ合衆国と日米和親条約を締結します。これを機に1639年以来200年以上続いてきた鎖国を解き、イギリス、フランス、オランダ、ロシアとも通商・国交を開いていきました。フランスのナポレオン3世から、駐日公使を通じて第2回パリ万国博覧会(1867年開催)への招待状が届いたのは、この激動の最中のことでした。
この招待を受けた際に、実は薩摩藩は幕府の命令を待たずに独自に「薩摩・琉球国」としてパリ万博への出展を進めていたそうで、万博への参加を即答していなかった幕府も薩摩の動きに幕府が追随する形で参加を決定したそうです。
佐賀藩は幕府に応じるかたちで、パリ万博への参加を決めました。1840年代から長崎の佐嘉商会を通じてオランダとの貿易に乗り出し、ヨーロッパ人の好みも把握しようと努めてきた佐賀藩にとって、万博は絶好のチャンスでした。

日本を代表する実業家、渋沢栄一は、この使節団に昭武の随員として加わり、上海、香港、サイゴン等へ立ち寄った記録やパリ万博の見聞、欧州の政治、財政、美術、工芸、軍事、風俗習慣まで、詳細に記録しています。
そのなかで、磁器や漆器をはじめとする日本の工芸品や日本女性が茶を振る舞う数寄屋造りの茶屋が大変な人気を博したことを「ヨーロッパ人好事家を幻惑すべき諸玩物」と記しています。「幻惑」とは誇張が過ぎると感じるかもしれませんが、実際に開催されたパリ万博ではそれを裏付けるかのような出来事が起こります。
その様子は次回のブログでお伝えしたいと思いますので、ぜひ皆様お楽しみに。